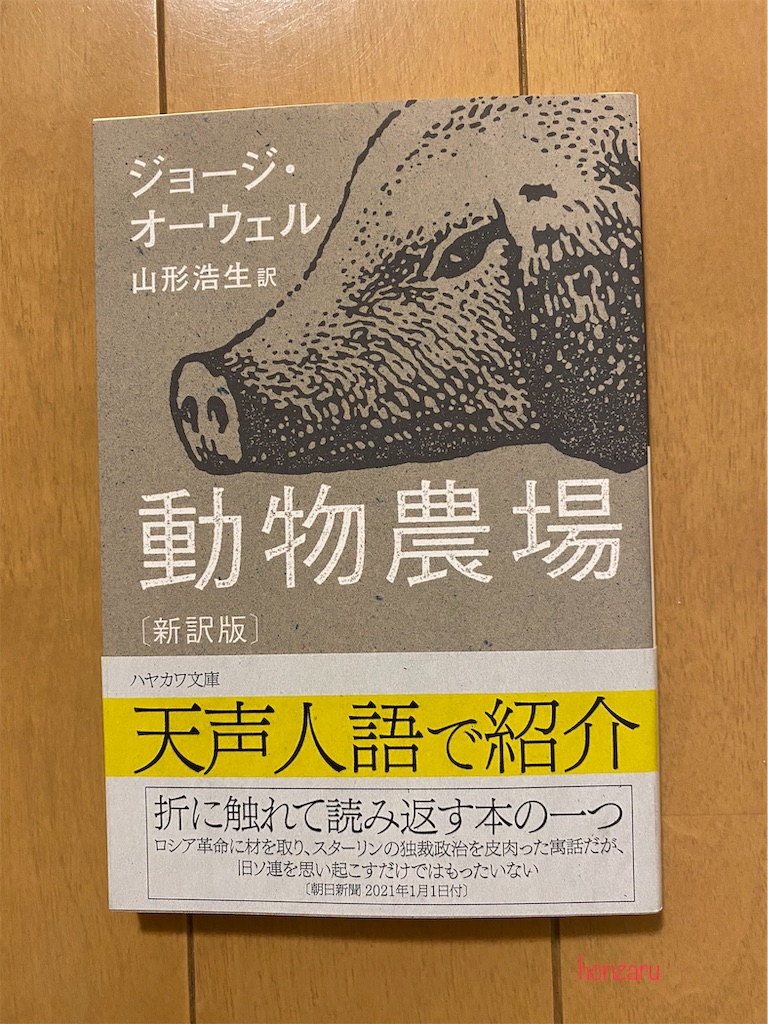ハーパーコリンズ・ジャパン 2021.5.31読了
全く知らない作家だし、なんなら出版社も聞いたことがない。2019年にオーストラリアで1番売れた小説らしい。壮大なタイトルと、ペラペラめくった時の字体と印刷のセンスにピンときて思わず手に取る。
溢れ出る比喩と空想世界が文章を彩る。どういう表現がぴったりくるのかわからないけれど、読みながら浮遊しているような感覚。結構珍しい独特の世界観なのだが、とても心地良い読書時間だった。
主人公はイーライという12歳の少年。空想が得意で素直で優しく、将来の夢はジャーナリスト。イーライの1つ歳上の兄はひとことも口をきかない。言葉を話せないのではなく敢えて話さない。話す代わりに空で文字を描く。イーライはいつもそれを読み取る。聡明な兄のことをイーライは誰よりも尊敬している。
この兄弟と両親、そして父の代わりとなるライル、さらにイーライの1番の親友である元脱獄王のスリムらと共に、悲しいけれど希望に満ちた冒険譚が繰り広げられる。読み終える頃にはイーライはたくましく成長する。
扱われているのは犯罪、脱獄、麻薬取引などダークなものなのに、イーライが語るそれは全く重苦しい感じがしなくて、むしろ虹がかかったかのようにすっきりと清々しい。どうしてだろう?イーライが善良な人間になるために常に前向きであることと独特な文体が理由かもしれない。
手紙を書く時には「ディテールを具体的に書け」とスリムはイーライに伝える。「堀の中の連中は、日常生活のつまらんディテールに飢えてる。自分ではもう経験できないわけだからな」手紙を書く相手に選んだのは、かつてスリムが入っていた刑務所にいる銃の密輸入で服役しているアレックス。
つまらない日常の些細なあれこれに飢えているということは、単なる日常が実は1番大切なものだということ。その積み重ねが人生を彩る。そもそもこの小説自体、通してディテールが具体的だ。ちょっとした風景、僅かな心の動き、流れてくる音楽、テーブルにある食べ物、そしてイーライの空想の産物さえも細やかな表現で、まるでそこに生きているかのようだ。