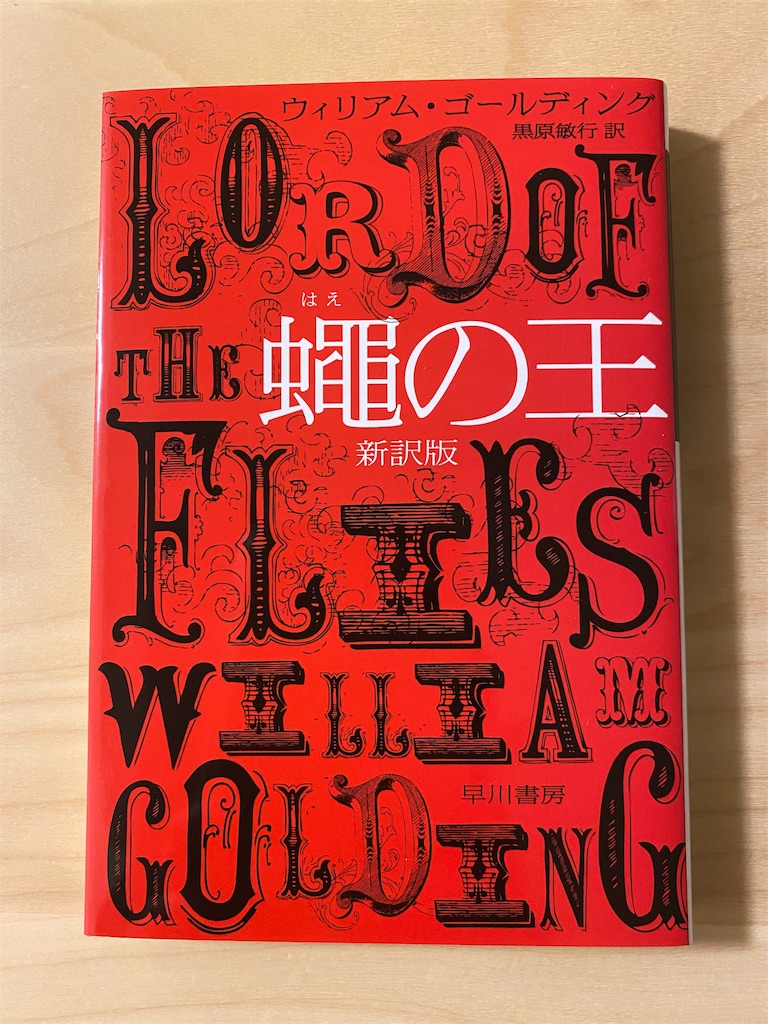『ラウィーニア』アーシュラ・K・ル=グウィン 谷垣暁美/訳
河出文庫 2021.2.15読了
実は私は『ゲド戦記』をちゃんと読んだことがない。アニメでも観ていない。ル=グウィンさんは『ゲド戦記』の作者であるが、他にも色々なSF・ファンタジー作品を残している。この『ラウィーニア』は著者最後の長編小説である。文庫のジャケットだけ見るとインドの小説なのかと勘違いする。
久しぶりに壮大なファンタジーを堪能した。…と言いたいところなのだが、序盤、ラウィーニアと詩人が語り合う場面はファンタジーに感じていたのに、途中からは古代ローマの史実に基づいた歴史小説のように思えた。
おそらく、古代ローマに実際にいた・あったであろう名前・地名が登場したからだろう。先月ジョン・ウィリアムズ著『アウグストゥス』を読んだからかもしれない。ファンタジーはたいてい著者が一から全てを作り出した名前が多いのに。
古代ローマの詩人ウェルギリウスが残したとされる『アエネーアス』という叙事詩に登場するのがこの作品の主人公ラウィーニアだ。詩では脇役でほとんど存在感がないようだが、ル=グウィンさんがこの小説で生き返らせた。なんと77歳でこの作品を完成させたそう。
古代ローマは領地を巡る争いが絶えない。そしてラティウム王の娘ラウィーニアは、誰が自分の婿になるのか気が気ではない。婿選びも、領地拡大に伴う政略結婚が世の常。それでも、詩人からの言霊を信じて両親に立ち向かう。女性目線で古代ローマを生き生きと力強く生きた彼女は尊かった。
ラウィーニアは詩人から未来に何が起こるのかを聞かされる。それを誰にも話さず大事なものとし心の糧として生きていくのだが、やはり自分の運命を先に知るなんて絶対嫌だな。
解説によると、詩人ウェルギリウスはアウグストゥスの側近だったとか。当時の女性は脇役であり表に出る幕がなかったそう。まさにわきまえていた。だからか女性目線のこの作品がとても新鮮なのかもしれない。もちろんこれもル=グウィンさんの妄想だけど。たまには異世界に没頭できる作品も良いものだ。