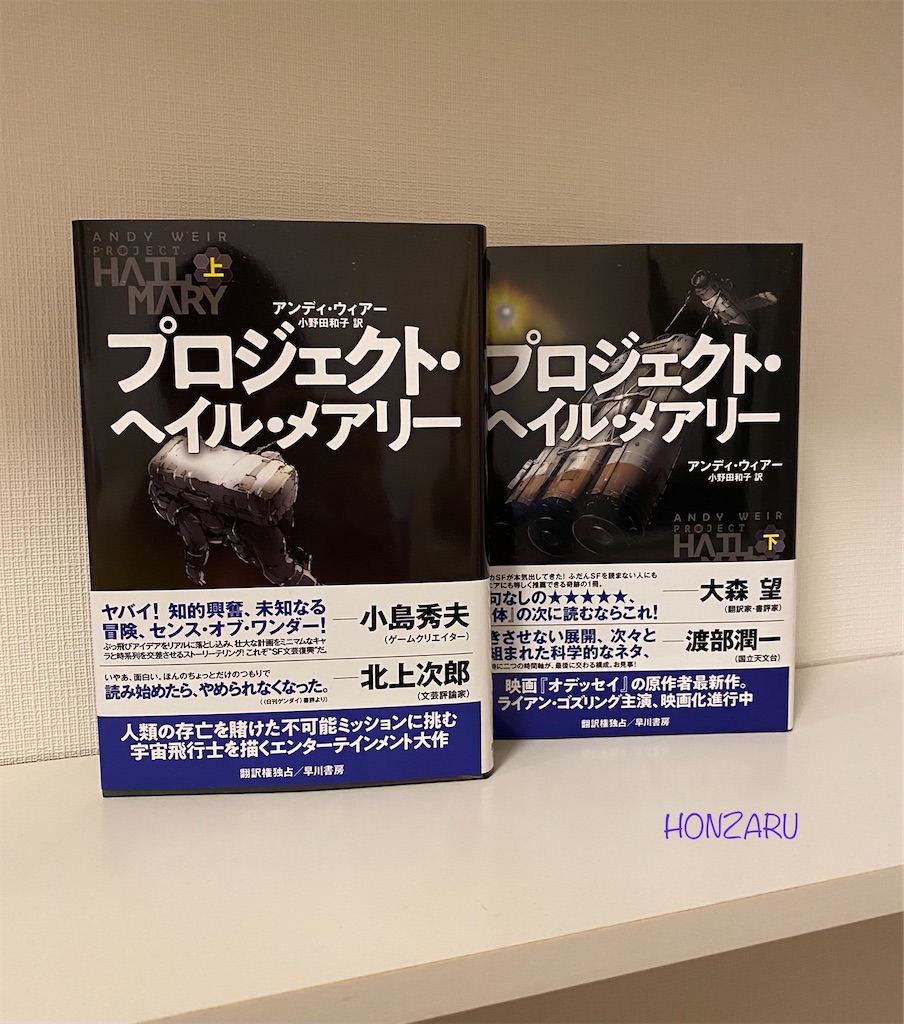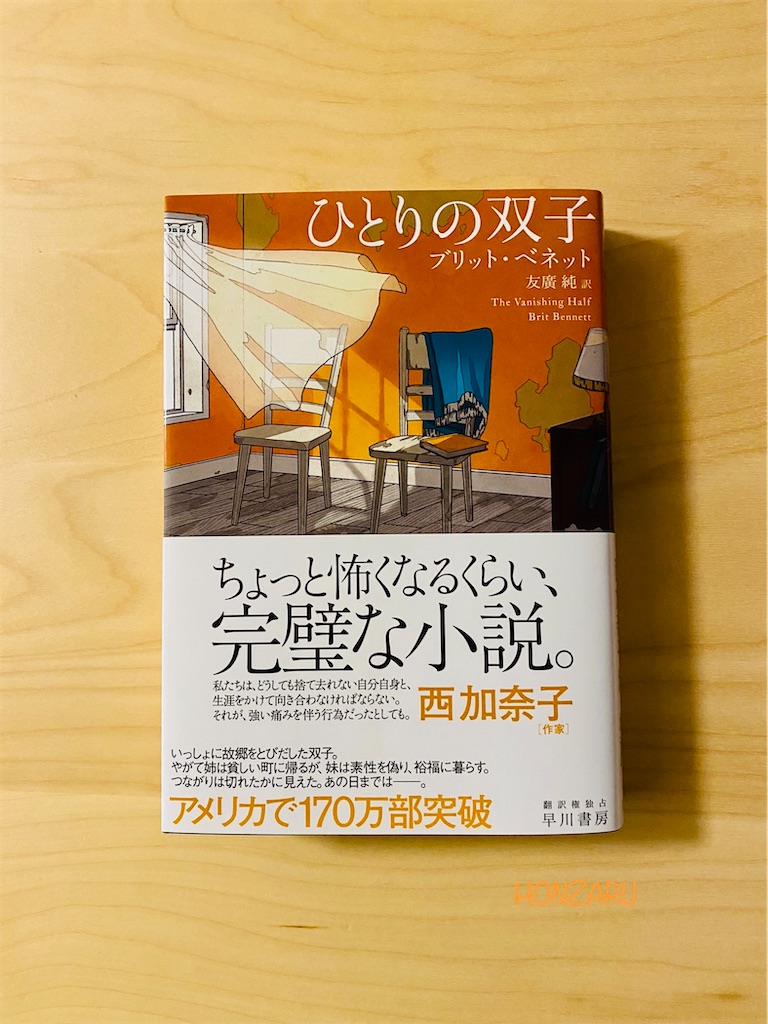
『ひとりの双子』ブリット・ベネット 友廣純/訳 ★★★
早川書房 2022.4.17読了
読み始めてすぐに、これは自分の好きなタイプの作品だと感じた。まずストーリーが抜群におもしろい。そして何より登場人物たちの息づかいが真に迫り感情に訴えかけてくる。どのキャラクターもその懸命な生き方に心をえぐられるのだ。特にアーリーとリースの優しさと強さには震える。じっくりゆっくり大事に読んだのだが、最後は読み終えるのが惜しくなってしまった。
マラードという小さな街から双子の姉妹が消えた。父親を亡くした記憶と貧困から、そして自分を変えたいと故郷を捨てたのだ。しかし姉のデジレーは子供を連れて町に戻ってくる。一方で妹のステラは身分を偽り裕福に暮らしていた。2人は本当に離れ離れになってしまったのかー。
アメリカには未だ人種問題が根強いことを改めて感じ、それによりもたらされる心の傷は一生癒えないのだと思った。見た目の肌の色ではなく、黒人の血が一滴でも混ざっていたら黒人となる。もちろん人種に優劣はない。それが何故こんなにも差別になってしまうのか。
黒人の女性が白人に成り切って生きること。周りを騙すことができればそれが「本当」になるなんてことあるのだろうか。見た目だけで白人と黒人を区別するのであれば、ステラのことを白人だと疑わなかった周りにとっては本当になる。ただ、偽る自分にとっては相手をも自分をも欺くという二重の重荷がのしかかる。
邦題は『ひとりの双子』になっているが、実際の原語タイトルは『The Vanithing Harf (ヴァニシング ハーフ)』、解説によると直訳で「消えゆく片割れ」である。直訳だとなんとも哀しい雰囲気を帯びている。確かに、この物語は哀しみを含んでいるが、邦題のほうがしっくりくる。例え離れ離れになったとしても双子であったこと、2人はどこかで繋がっていることが生きるための心の糧になる。
物語は叙情的かつミステリアスで、最初から最後まで大満足できた。おもしろかったというのは同時に真剣に向き合う問題も多かったからだ。人種問題だけでなく、貧困、暴力、トランス・ジェンダー、女性蔑視などあらゆる分野を内包する。最後はもう、母と娘の絆に尽きると思う。
帯にある西加奈子さんの文章に思わず反応してしまった。帯の文句に騙されることも多々あるのだけど、これは文句なくおもしろかった。これからも死ぬまで(目が見えなくならない限り)読書生活は続くと思うけれど、読める本の冊数は限られる。なるべく良本を読むために、そして自分にとって大事な本に出会うために、選書の眼を養うこともまた大切だと思った。だってこういう本になるべく多く出会いたいから。
最近の早川書房の外文担当編集者さんはかなり頑張っていると思う。毎月続々と新たな作品・作家を日本に広めてくれている。訳者の友廣さんの名前をどこかで見たことがあると思ってきたら、ディーリア・オーウェンズ著『ザリガニの鳴くところ』を訳した方だった。あの作品も傑作だった。